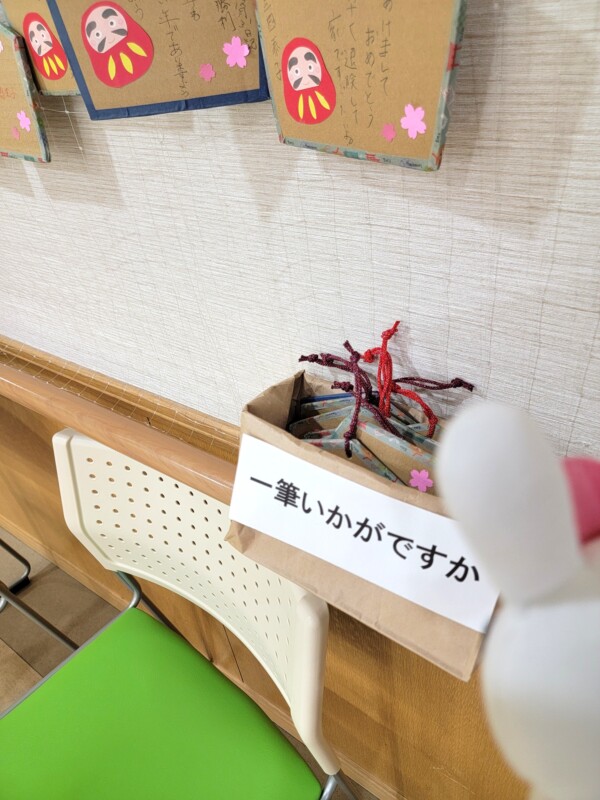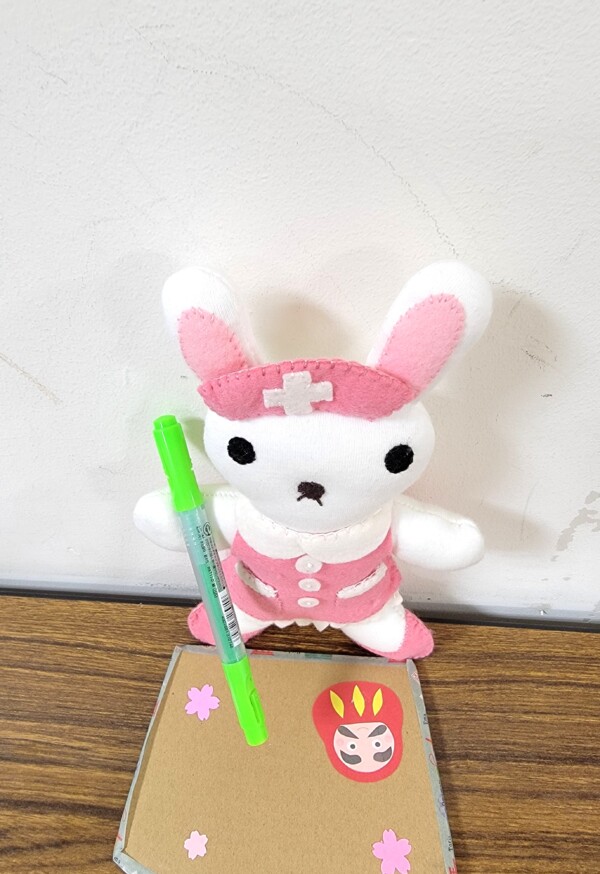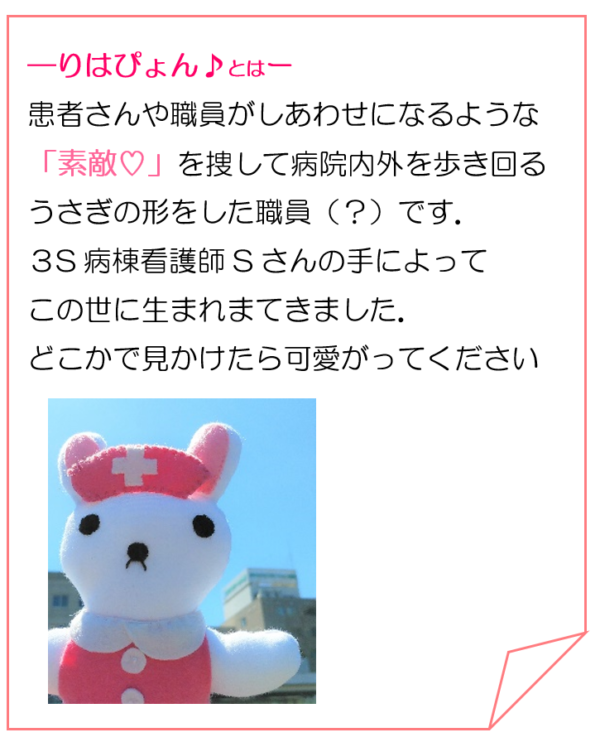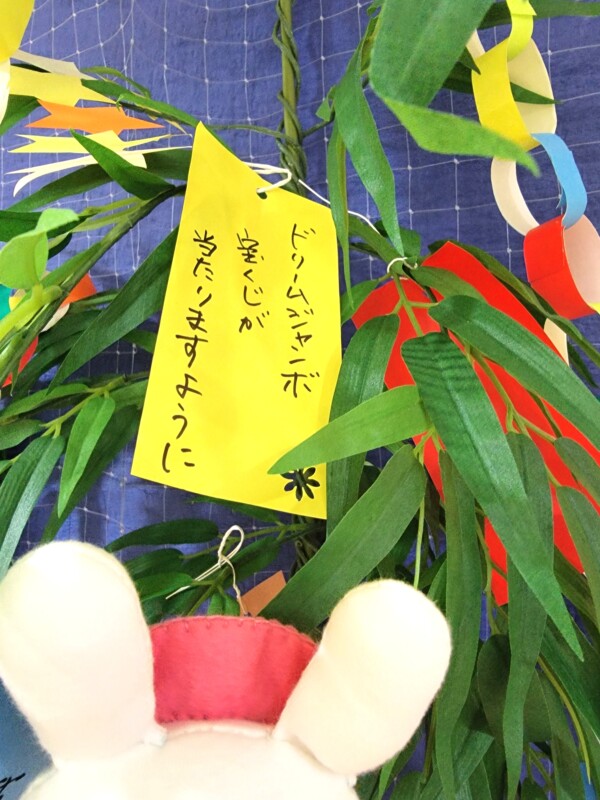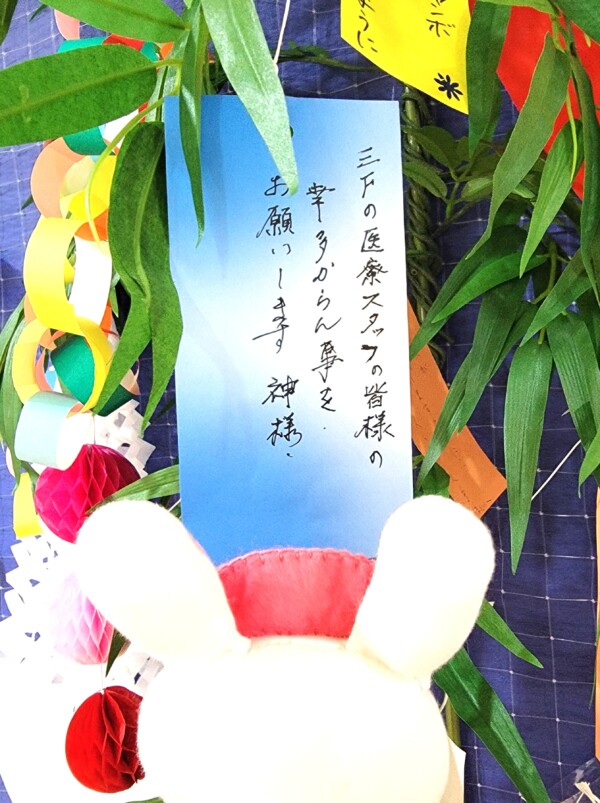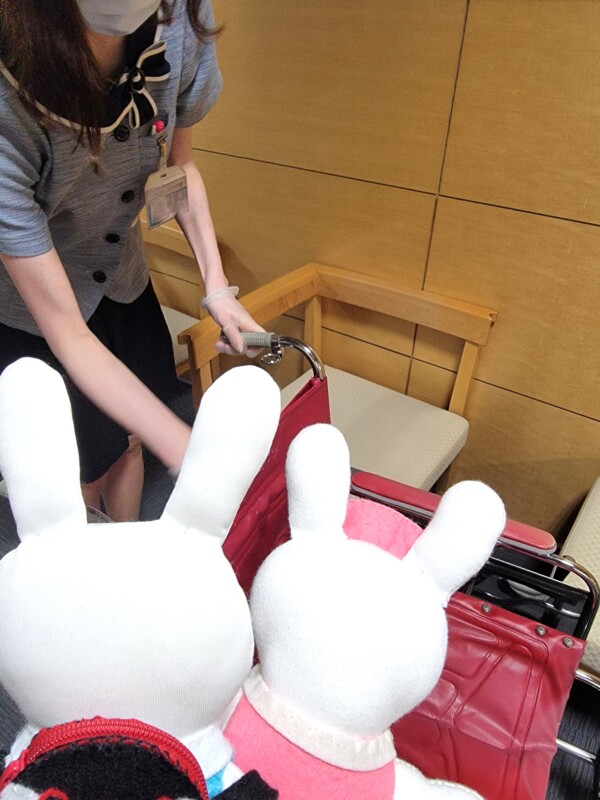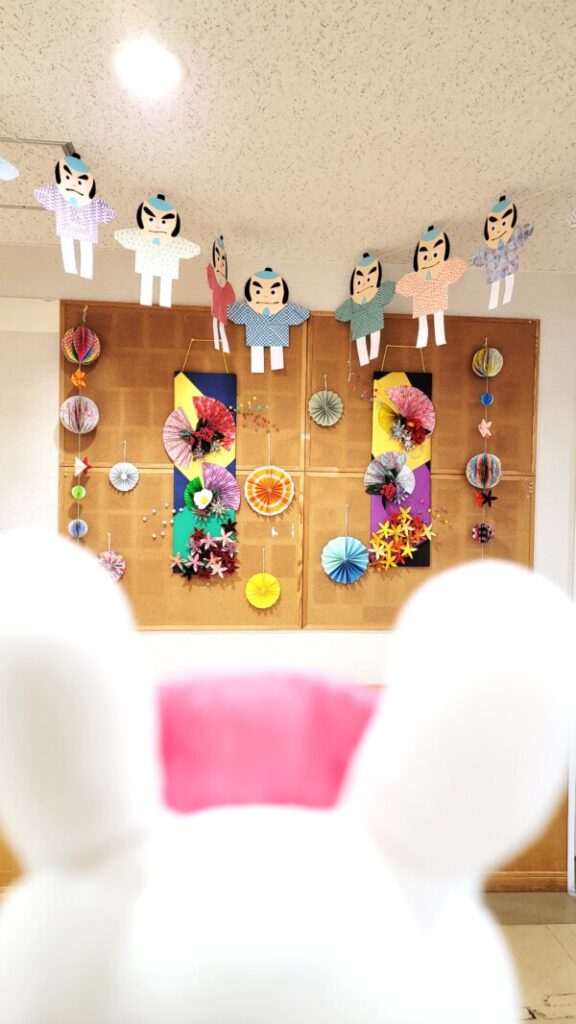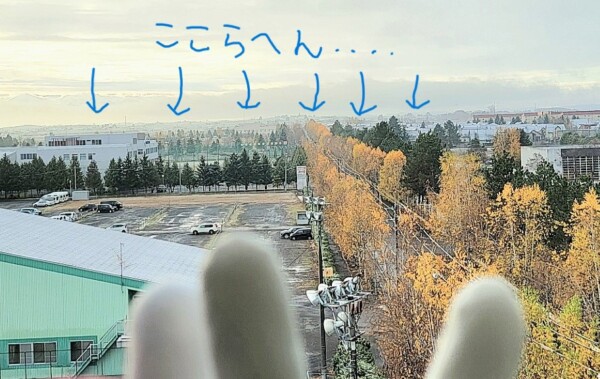2025年大晦日、TVで紅白歌合戦を見た。今年で紅白出場は最後と宣言した歌手Gをみるためだ。大スターの最後の出場なのにどうしてトリでないのだ?といった不満をある知人に話したところ、知人はこういった「彼はいつでもどこでも置かれた状況で全力で走って一生懸命歌う。ただそれだけだ。それがいいのだ。それが見ている人をどんなに元気づけることか、彼は知っている。トリとかそういうのは彼にとってどうでもいいことだ。」
目から鱗が落ちた。確かにTVの向こうの彼はいつも通り全力で会場を駆け巡り、息切れひとつせず最後まで笑顔で歌い切った。一昨年も去年も、そして今年も。
四半世紀以上前の自分の曲を同じ音程で、同じ振付で唄うのって、どれだけのプロができるのだろう?信じられない歌唱力に体力。年齢は古希と言っていた。彼の見た目は確かにそうは見えない。だがそれ以上にもっとすごいのはその精神だ。大スタ―にもかかわらず傲慢にならず常に謙虚な姿勢。そして新しいことにもチャレンジし続ける。大スターにもかかわらずバラエティとか歌番組のコラボもノリノリにこなして、しかも面白い!なにより本人が積極的で本当に楽しそうなのだ。紅白でも他の歌手の応援や有志参加のダンスも一番楽しそうだった。昭和・平成・令和という時空を超え、Gというスターであり続ける奇跡。いろいろなことを経験してすべて乗り越えてきた人間にしかだせないオーラ。
『置かれた場所で咲きなさい』という渡辺和子さんの本を思い出した。「置かれた場所で諦めず、最善を尽くすことで、幸せになりなさい。それがきっとあなたの周りの人をも幸せにするから」という内容である。確かにGをみている我々は元気になった。勇気をもらった。Gも笑顔だった。『置かれた場所で咲きなさい』とは、自分が笑顔で幸せに生き、周囲の人々も幸せにすることによって、神が、あなたをここにお植えになったのは間違いでなかったと、証明することなのです。渡辺和子さんは言う。
「置かれた場所で咲きなさい」
という価値観が尊いことに異論はない。置かれた状況で全力を尽くすべきだと思う。
しかしその上で新たなチャレンジに全力で挑むこともありだと思う。「今年で70歳。これを区切りとして、新しいアーティストに思いをつなげたい」と言うG。これからも新たなチャレンジをし続けるのだろう…。今までどうもありがとうございました!
来年から紅白にGの歌声と笑顔がないのは、とても寂しい。
旭川リハビリテーション病院副院長